ページID:11848
更新日:2025年10月22日
ここから本文です。
子どもの定期予防接種のご案内
子どもの定期予防接種は、荒川区が発行する接種予診票により、東京23区の協力医療機関において無料で予防接種を受けることができます。原則、接種予診票は、接種対象年齢が到達する頃から一斉発送をいたしますが、他自治体から荒川区へ転入された場合、または送付した予診票を紛失した場合は、以下のフォームからお申し込みください。
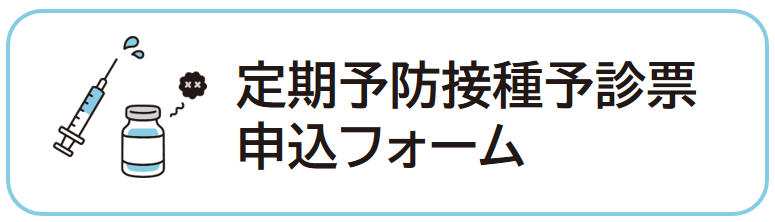
【電子申請】定期予防接種予診票申込フォーム(転入・紛失・日本脳炎ワクチン早期接種開始及び特例対象等による新規発行)(外部サイトへリンク)
お知らせ
麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)については、ワクチンの流通事情により、区内協力医療機関において接種が困難な状況になっております。この状況を受け、国は令和6年度に定期接種対象者であった方で規定の期間内に接種を受けることができなかった方を対象に、接種期間の延長措置をとることとしました。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
目次
予防接種を受ける際の一般的な注意事項
予防接種は体調のよいときに受けるのが原則です。保護者の方はお子さんの体質、体調など健康状態によく気を配ってください。
予防接種の効果や副反応などについて理解した上で、接種に同意したときに限り、接種が行われます。
予防接種を受けることができない場合
- 明らかに発熱(通常37.5℃以上)している
- 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかである
- その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがあることが明らかである
- その他、医師が不適当な状態と判断した場合
予防接種を受ける際に注意を要する場合
以下に該当する場合、かかりつけ医に必ず前もってお子さんを診てもらい、予防接種を受けてよいか判断してもらってください。予防接種を受ける場合は、かかりつけ医のところで接種を受けるか、診断書または意見書などをもらってから接種を受けるようにしてください。
- 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気や発育障害などで治療を受けている
- 予防接種を受けた2日以内に、発熱、発疹、じんましんなどアレルギーと思われる異常が見られたことがある
- 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがある
- 過去に免疫不全の診断を受けている、または近親者に先天性免疫不全症の方がいる
- ワクチンの製造過程における培養に使う卵の成分、抗菌薬、安定剤などにアレルギーがあると言われたことがある
予防接種を受けた後は
- 予防接種を受けた後30分間程度は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐ連絡をとれるようにしておきましょう。
- 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
- 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
- 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
- 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
接種予診票の発送スケジュール
出生届(生まれた日から14日以内に届出が必要です)の受理が遅れた場合や、発送時期の前後に荒川区へ転入された場合などの理由により、接種予診票が以下のスケジュール通りに届かない可能性があります。
発送時期を過ぎてしばらく待っても接種予診票が届かない場合は、荒川区保健所健康推進課までご連絡ください。
0歳のときに接種する予防接種
|
発送時期 |
ワクチンの種類 |
枚数 |
|---|---|---|
|
誕生月の翌月下旬 |
5種混合ワクチン(初回) | 3回分 |
|
小児用肺炎球菌ワクチン(初回) |
3回分 |
|
|
B型肝炎ワクチン |
3回分 |
|
|
ロタウイルスワクチン |
3回分 |
|
|
BCGワクチン |
1回分 |
1歳から2歳のときに接種する予防接種
|
発送時期 |
ワクチンの種類 |
枚数 |
|---|---|---|
|
1歳となる前月 |
5種混合ワクチン(追加)(※注釈1) |
1回分 |
|
小児用肺炎球菌ワクチン(追加) |
1回分 |
|
|
麻しん風しん混合ワクチン(1期) |
1回分 |
|
|
水痘ワクチン |
2回分 |
|
|
1歳児プチ健診受診票(※注釈2) |
1回分 |
※注釈1 令和6年(2024年)1月以前に生まれた方には、「4種混合ワクチン(追加)1回分」と「ヒブワクチン(追加)1回分」を送付しています。
※注釈2 1歳児プチ健診では、1歳から1歳3か月未満の間に、麻しん風しん混合ワクチンを接種されるお子さんの身長と体重を計測しています。詳細は以下のリンクをご確認ください。
乳幼児健診【1歳児プチ健診】
※注釈3 おたふくかぜは任意予防接種です。区では、おたふくかぜ予防接種費用の一部を助成しています。詳細は以下のリンクをご確認ください。
おたふくかぜ予防接種費用の助成
3歳以降に接種する予防接種
|
発送時期 |
ワクチンの種類 |
枚数 |
|---|---|---|
|
3歳の誕生月 |
日本脳炎ワクチン(1期)(※注釈) |
3回分 |
|
年長クラスに入る年の3月下旬 |
麻しん風しん混合ワクチン(2期) |
1回分 |
|
9歳の誕生月 |
日本脳炎ワクチン(2期) |
1回分 |
|
11歳の誕生月 |
2種混合DTワクチン |
1回分 |
|
中学1年に入る年の3月下旬(女子のみ) |
HPV(子宮頸がん予防)ワクチン |
2回分 |
※注釈 日本脳炎ワクチンは生後6か月から接種可能です。3歳になる前に接種をご希望の場合は接種予診票を発行しますので、荒川区保健所健康推進課窓口にお越しいただくか、お電話またはページ上部にあります電子申請からお申込み下さい。
異なるワクチン間の接種間隔
各ワクチンの接種時期と接種間隔は以下のページをご確認ください。
子どもの定期予防接種の接種時期・接種間隔
| ワクチンの区分 | ワクチンの種類 |
|---|---|
|
注射生ワクチン |
BCG、麻しん風しん混合、水痘、おたふくかぜ |
|
経口生ワクチン |
ロタウイルス |
|
不活化ワクチン |
5種混合、4種混合、ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、日本脳炎、2種混合DT、HPV |
- 注射生ワクチンを接種した後、それとは異なる注射生ワクチンを接種する場合のみ、27日以上の間隔をあけて接種してください。
(例)麻しん風しん混合ワクチンを接種した後に、水痘ワクチンを接種する場合等 - それ以外のワクチンの組み合わせは、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、次のワクチンの接種を受けることができます。
予防接種を受ける際の保護者の同意・同伴
|
接種を受ける方の年齢 |
保護者の同意・同伴 |
|---|---|
|
満12歳以下 |
同意・同伴ともに必要 |
|
満13歳以上満15歳以下 |
あらかじめ、接種することの保護者の同意を予診票上の保護者自署欄で確認できれば同伴は不要 |
|
満16歳以上 |
同意・同伴ともに不要(接種を受ける方本人による同意で接種を行います) |
保護者が同伴できない場合
接種を受ける方が満12歳以下で、接種当日に保護者が同伴することができない場合、普段からお子さんの健康状態を良く知っている方(祖父母等)に限り、代理で同伴することができます。
接種を受ける前に保護者・同伴者それぞれが以下の委任状に必要事項を記入し、接種当日に医療機関へ持参してください。
予防接種証明書の発行
- 母子健康手帳及び荒川区の予防接種台帳で確認できる接種履歴について、証明書を発行しています。
- 証明書は、日本語版・英語版の2種類です。
- 証明書1枚につき300円の手数料がかかります。荒川区保健所健康推進課の窓口にて現金でお支払いいただくか、金融機関での納付書払いのどちらかになります。
- 証明書の申請から発行まで1週間前後かかります。時間に余裕を持ってご申請ください。
申請に必要な書類
- 予防接種に関する証明書交付申請書(PDF:24KB)
(参考)予防接種に関する証明書交付申請書【記入見本】(PDF:25KB) - 母子健康手帳のコピー(母子健康手帳がお手元にある方のみ)
- 被接種者及び申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)のコピー
※注釈 証明書の窓口受け取りをご希望で、受け取りに来られる方が申請者と異なる場合は、委任状(PDF:4KB)も併せて提出してください。
申請先
〒116-8507 東京都荒川区荒川2-11-1
荒川区がん予防・健康づくりセンター内
荒川区保健所健康推進課予防接種係
(予防接種に関する証明書交付申請書在中)
長期療養特例
定期予防接種の対象だった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病(免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病や、免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病)等の特別の事情があることにより接種を受けることができなかったと認められる者については、特別の事情がなくなった日から起算して2年間、定期予防接種の対象となります(一部のワクチンを除く)。
詳細は荒川区保健所健康推進課までお問い合わせください。
お問い合わせ
健康部健康推進課予防接種係
〒116-8507荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:3901)
ファクス:03-3806-0364