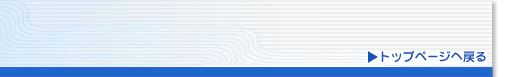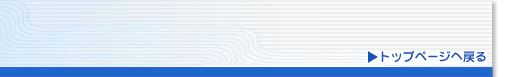| 三春滝サクラや荒川区の保護樹木に指定されているケヤキ、イチョウの木が植えられており、四季折々の自然を楽しむことができます。
創建の年は明らかではありませんが、神社に残っている棟札の最古のものには至徳2(1385)年と記されているので、それ以前の建立であることが分かります。応神天皇と末社の神々を祀り、農工商の神様として地域の人々に親しまれてきました。また、学業成就、交通安全、商売繁盛、除災招福、病気平癒、金運などの御利益があるとされており、各種のお守り(300〜1000円)も境内で販売されています。
尾久宮前小学校の児童が八幡堀を発見するきっかけとなった古地図の原本である「上尾久村村絵図」は、この神社の所有物で、平成2年に荒川区の有形文化財に指定されました(現在は荒川ふるさと文化館で保管)。
 |

八幡堀プロムナードと、尾久村絵図の紹介が並んで建っています。 |
また、毎年2月(祈年祭)と8月(例大祭)と12月(新嘗祭)にはお祭りが行われます。8月の例大祭(8月の第1土・日に行われる)は4年に1度、神幸祭と呼ばれる盛大なものとなり、馬や山車や御輿の行列が尾久の地域をねり歩きます。その神幸祭がちょうど今年にあたります。
|