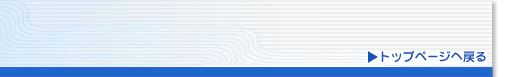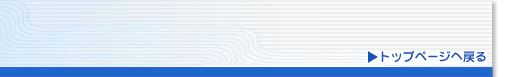|

手づくり絵本「ぼくらの音無川」 |
八幡堀とは、今は暗渠となった音無川から分流した用水路で、隅田川へと注いでいました。
荒川がかつて農村地帯であったことを示すこの掘り跡は、住民からの要望も取り入れ「すいろみち 八幡堀」景観整備基本設計として荒川区により整備されました。
散策途中、絵タイルや、川の流れをイメージする意匠など、所々に発見があることでしょう。
時間が許せば、少し足を延ばして尾久宮前小学校あたりの旧八幡堀も散策してみてください。 八幡堀プロムナードと名付けられたこの道は、43人の小学生の大発見によってできたものです。そこにはこんな物語が秘められています。
昭和60(1985)年、地域学習をすることになった区立尾久宮前小学校の3年3組のある児童が、家から江戸時代の古地図の写しを持ってきました。児童たちはそこに今は流れていない何本もの川を見つけます。不思議に思って、地域に住んでいるお年寄りなどを訪ね、話を聞くうちに、どうやら自分たちの住む町には江戸時代から大正時代まで、八幡堀という用水路が存在していたらしいと知ります。調査の段階で導かれた郷土への愛着は、水路が見られないのなら、せめて音無川の跡でも良いから歩きたいという願いに変わり、先生、親、地域の人も含めて一緒に音無川の跡を訪ねるサイクリングを決行しました。 その学習の記録は、手づくり絵本「ぼくらの音無川」にまとめられ、生徒達の宝物になりました。
その後、児童の父母や教師からも「子供にまちの歴史を学べる場所を」という陳情が荒川区にあがり、八幡堀プロムナードの整備が決まりました。
このプロムナードは小学校から八幡堀児童公園まで断続的に続き、児童が描いた絵タイルが鮮やかに埋め込まれています。
荒川区では、「こんなに意欲をもって学習した次代を担う子供たちのために、何か記念を」ということで、八幡堀児童公園に5メートルの高さのモニュメントも作りました。
地域住民と行政のコラボレーションで生まれたこの道は、西尾久住民の誇りです。
|