ページID:2585
更新日:2026年2月3日
ここから本文です。
住宅用家屋証明
更新履歴
NEW 令和8年2月2日より、Logoフォームにおける電子申請を開始いたしました(ただし、領収書は発行できません)
住宅用家屋証明書のご案内
- 住宅用家屋を新築または取得した個人の方が、1年以内に登記する際、「住宅用家屋証明書」を添付すると、登録免許税が軽減されます。(租税特別措置法72条の2から75条)
- 証明書の交付には、一定の要件を満たすことが必要です。
- 「住宅用家屋証明書」は、その建物の適法性を担保するものではありません。
軽減される税率表
| 項目 | 通常 | 住宅用家屋証明を受ける住宅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般住宅 | 特定認定長期優良住宅 | 認定低炭素住宅 | ||||||||
| 所有権の保存登記 | 4/1000 | 1.5/1000 | 1/1000 | 1/1000 | ||||||
| 所有権の移転登記 (売買、競落に限る) |
20/1000 | 3/1000 | 1/1000(注) (一戸建ては2/1000) |
1/1000(注) | ||||||
| 抵当権の設定登記 | 4/1000 | 1/1000 | 1/1000 | |||||||
※注釈1 建築後使用されたことのないものに限ります。
※注釈2 特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率は、1/1000に軽減されます。
発行にあたっての要件
個人が新築した家屋について証明を受けようとする場合
- 建築後1年以内の家屋であること。
- 自己の居住の用に供するための住宅であること。
- 登記記録上の床面積が50平方メートル以上であること。
- 登記記録上「居宅」となっていること。(店舗等の併用住宅の場合は、その家屋の床面積の90%を超える部分が専用住宅であること。)
- 区分所有される建築物は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
建売住宅、分譲マンション(建築後使用されたことのない家屋)について証明を受けようとする場合
- 取得後1年以内の家屋であること。
- 自己の居住の用に供するための住宅であること。
- 登記記録上の床面積が50平方メートル以上であること。
- 登記記録上「居宅」となっていること。(店舗等の併用住宅の場合は、その家屋の床面積の90%を超える部分が専用住宅であること。)
- 建築後、使用されたことがないこと。
- 区分所有される建築物は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
中古住宅、中古マンション(建築後使用されたことのある家屋)について証明を受けようとする場合
- 取得後1年以内の家屋であること。(所有権移転登記の場合は、取得原因は、売買または競落に限ります。)
- 自己の居住の用に供するための住宅であること。
- 登記記録上の床面積が50平方メートル以上であること。
- 登記記録上「居宅」となっていること。(店舗等の併用住宅の場合は、その家屋の床面積の90%を超える部分が専用住宅であること。)
- 区分所有される建築物は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
- 昭和57年1月1日より前に建築された家屋については、下記書類のいずれかが必要となります。
| 証明書 | 備考 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐震基準適合証明書(原本提出) | 住宅取得の日前2年以内に証明のための調査が終わっていることが必要です。 | ||||||||||||||
| 住宅性能評価書(写し提出) | 住宅性能評価書は住宅の売買をする前に、売主が取得してください。住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写しで、住宅取得の日2年以内に評価されたもので、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価が、1~3級の範囲であることが必要です。 | ||||||||||||||
| 住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(写し提出) |
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に規定する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約のうち、必要要件に適合し、住宅取得の日前2年以内に締結されたものであることが必要です。必要要件については事前にお問い合わせください。 |
||||||||||||||
個人が宅地建物取引業者から取得した特定のリフォーム工事がされた建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合
増改築等工事証明書の提出(写し可)が必要です。要件や必要書類についてはお問合せください。
申請に必要な書類
| 自分が建築主として新築した場合 | 建築後使用されたことのない家屋を取得した場合 | 既存の家屋を取得した場合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保存登記 | 保存登記又は移転登記 | 移転登記 | ||||||||
| 入居済 | 未入居 | 入居済 | 未入居 | 入居済 | 未入居 | |||||
| 長期優良住宅・低炭素住宅の場合は申請書の副本と認定通知書 | 写し提示 | 写し提示 | 写し提示 | 写し提示 | ||||||
| 登記完了証と登記申請受領証または登記事項証明書 注1 | 写し提示 | 写し提示 | 写し提示 | 写し提示 | ||||||
| 登記事項証明書 注2 | 写し提示 | 写し提示 | ||||||||
|
住民票の写し (コピー) 注3(発行日から3カ月以内のもの) |
写し提示(コピー) |
写し提出 |
写し提示 (コピー) |
写し提出 (コピー) |
写し提示 (コピー) |
写し提出 (コピー) |
||||
| 売買契約書、売渡証書または登記原因証明情報 注4 | 写し提示 | 写し提示 | 写し提示 | 写し提示 | ||||||
| 家屋未使用証明書(原本) 注5 | 原本提出 | 原本提出 | ||||||||
| 未入居の申立書(本人署名・押印)注6 | 原本提出 | 原本提出 | 原本提出 | |||||||
|
現居の家屋の処分方法を示す書類 注7 ※必ずご参照ください |
写し又は原本提出 |
写し又は原本提出 |
写し又は原本提出 |
|||||||
注釈
- 住宅用家屋証明申請書・証明書(申請書の押印は不要になりました。)
- 確認済証及び検査済証は原則不要ですが、必要に応じて提示を求める場合がございます。
(例)売買契約書等の売主と未使用証明書の証明者が異なる場合
(例)建主が個人のときに、建主の増減があった場合 など
- 注1 登記完了証と登記申請受領証、または登記事項証明書をご提示ください。確認後、返却いたします。(次の1~3のいずれか)
- 登記完了証(書面申請)と登記申請受領証(新築年月日、床面積が確認できるもの)
- 登記完了証(電子申請)のみ(新築年月日、床面積が確認できるもの)
- 登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスにより取得したものは、照会番号と発行年月日が記載されたもので、発行後100日以内で未使用のもの)
- 注2 登記事項証明書をご提示ください。確認後、返却いたします。(インターネット登記情報提供サービスにより取得したものは、照会番号と発行年月日が記載されたもので、発行後100日以内で未使用のもの)
- 注3 住民票の写し(コピー)をご提示いただき、確認後、返却いたします。ただし、未入居でのご申請の場合は、住民票の写し(コピー)の提出が必要となります。(発行日から3カ月以内のもの)
- 注4 売買契約書、売渡証書または登記原因証明情報(写し)をご提示ください。確認後、返却いたします。
競落の場合には、代金納付期限通知書(写し)をご提示ください。 - 注5 家屋未使用証明書(売主所在地、売主名称、代表者名及び免許番号が確認でき、売主の押印(代表者印)がなされているもの。)
売主の方が発行する原本をご提出ください。(建築後使用されたことのない家屋を取得した場合に必要となります。) - 注6 未入居の申立書(本人署名と押印があるもの。)原本をご提出ください。
- 未入居の場合は、未入居の申立書と「現居の家屋の処分方法を示す書類」の提出が必要となります。なお、入居予定日までの期間は、未入居の申立書に記載した申立日から2週間までとなります。
- 申立日より入居予定日が2週間を超える場合は、「現居の家屋の処分方法を示す書類」に加え、その理由に応じた書類と後日新住所地の住民票の写し(コピー)の提出が必要です。詳しくはQ&Aをご参照いただくか、またはお問合せください。
- 宅地建物取引業者が家屋の仲介取引をした場合、買主の入居見込みを証する確認書の提出でも可能です。(押印は不要です。)
注7 現居の家屋の処分方法を示す書類
持家を売却
売買契約書等売却を証する書類等の写し(媒介契約書の場合は契約締結期間内のもの)
持家を賃貸に出す
賃貸借契約書の写し等賃貸借を証する書類等の写し(媒介契約書の場合は契約締結期間内のもの)
借家を退去する
賃貸借契約書等の写し(賃貸借契約期間内のもの)
社宅を退去する
社宅入居証明書(原本提出)
親族等の住宅から退去する
親族等の証明書(親族等の署名・押印)と親族等の住民票の写し(コピー)
抵当権設定登記のみを行う場合
抵当権設定登記を行う場合、上記の必要書類のほかに下記書類のいずれの写しが必要となります。
- 抵当権設定に係る設定契約書
- 金銭消費貸借契約書
- 保証契約書、または登記原因証明情報の写し
当該住宅を新築(増築)または取得するために、資金の貸付を受ける場合に限ります。
※注釈 保存登記または移転登記と同時に抵当権設定登記を行う場合は、上記書類を省略できます。
申請に関するQ&A
|
お問合せ内容 |
回答 |
|---|---|
|
Q1.賃貸住宅に居住しており、更新契約書は作成しておりませんが、更新合意書や更新通知書があります。それらの書類の提出で住宅用家屋証明は取得できますか。 |
A1.物件の所在、契約期間、貸主及び借主の署名・押印が確認できれば、住宅用家屋証明書の添付書類として承ることは可能です。 |
|
Q2.賃貸住宅に居住しており、契約期間が切れた賃貸借契約書はありますが、更新契約書等を紛失してしまいました。どのような書類が必要ですか。 |
A2.更新契約書等を紛失してしまった場合は、下記のいずれかの書類をご提出ください。
|
|
Q3.賃貸住宅に居住しており、賃貸借契約書の写しを提出しますが、契約者名が旧姓の場合でも、賃貸借契約書のみの提出でよろしいですか。 |
A3.賃貸借契約書の契約者名が旧姓の場合、旧姓と新姓がわかる公的な証明書が必要となります。
|
|
Q4.現在親族等の持家に住んでいます。親族等の証明書のほかにどのような書類が必要ですか。 |
A4.親族等の住民票の写し(コピー)または、その家屋の所有者が親族等であることを確認するために登記事項証明書等が必要です。 |
|
Q5.現在親族等が借りている家屋に住んでいます。親族等の証明書のほかにどのような書類が必要ですか。 |
A5.親族等の住民票の写し(コピー)または、親族等が借主になっている契約期間内の賃貸借契約書の写しが必要です。 |
|
Q6.現在社宅に住んでいます。どのような書類が必要ですか。 |
A6.未入居の申立書に「社宅としての契約が終わる」旨の記載及び以下のいずれかの書類が必要となります。(自己が所有する建物ではないことを証明するため。)
|
|
Q7.申請者が単身赴任しているため、家族は新住所に住民票を移していますが、申請者は2週間以内に住民票を移すことができません。未入居の申立書のほかにどのような書類が必要ですか。 |
A7.赴任先のある在職証明書等(海外赴任の場合は在留証明書及び在職証明書等)と、入居済の家族の住民票の写し(コピー)が必要となります。 |
|
Q8.未入居の申立書の記載について、入居が登記の後になる理由はどのような事由が認められますか。 |
A8.荒川区では原則、次の2点のみ承っております。
|
|
Q9.申立日から2週間以内に入居することができません。未入居の申立書と「現居の家屋の処分方法を示す書類」のほかにどのような書類が必要ですか。 |
A9.入居予定年月日が2週間を超える場合は、その理由に応じた書類等が必要です。なお新住所地に入居後、すみやかに新住民票の写し(コピー)をご提出いただく必要があります。
※複数該当する場合は、それぞれの書類が必要です。 |
|
Q10.申立日から2週間以内に入居することができません。入居が登記の後になる理由はどのような事由が認められますか。 |
A10.未入居の申立書に「抵当権設定登記を急ぐ」または「権利保全」の理由に加え、入居が2週間を超える具体的な理由の記載が必要となります。(A9参照) |
|
Q11.引越の都合により、新住所地に住民票を移すことができません。その旨を記載した未入居の申立書を提出した場合、住宅用家屋証明書を取得することはできますか。 |
A11.引越の都合による住宅用家屋証明書の事前発行は行っておりません。ご了承ください。 |
| Q12.申請人が外国人の場合、申請書・証明書への氏名の書き方はどのようにすればよいですか。 | A12.住民票の記載通りにご記載ください。カナや通称名でのご申請は、住民票でその表記が確認できる場合にのみ承ります。 |
| Q13.共有名義の場合、持ち分の記載は必要ですか。 | A13.持ち分については証明できないため、記載しないでください。 |
| Q14.郵送での申請は受け付けていますか。 | A14.受け付けています。詳細は、郵送での申請をご覧ください。 |
申請手数料
- 1件につき1,300円
- 交付手数料のお支払いにキャッシュレス決済がご利用いただけます。
利用できるキャッシュレス決済サービス
※注釈1 キャッシュレス決済の場合は領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は現金で納付してください。
※注釈2 窓口で電子マネーのチャージはできません。事前に残高をご確認いただくようお願いいたします。
申請にあたってのご注意
- 申請者が共有名義(2名以上)である場合、氏名欄に(住所が異なる場合は住所も)連記してください。なお、持ち分については証明できないため記載しないでください。
- 個人の方が新築した家屋で、確認済証及び検査済証に記載のある建築主と、住宅用家屋証明を取得する申請者が異なる場合は、法務局に提出している上申書の写しが必要です。
- 家屋の「取得日」が申請日の翌日以降となる場合は証明できません。
- 提出いただく書類はお返しできませんので、必要に応じて写し等を用意してください。
- 申請件数が10件以上となる場合は、必ず事前にスケジュール調整を行ってください。また、調査が必要な場合にはお時間をいただきます。なお、部屋番号や氏名がわかる簡易的なリストの提出もお願いいたします。
※10件以上の場合のリスト(エクセル:11KB)ご自由にお使いください。 - 申請件数が10件未満の場合でも、内容によっては、翌日以降の発行となる場合がございますのでご了承ください。
- 「住宅用家屋証明書」の再発行はいたしません。
※注釈 認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は、所得税の住宅ローン控除の手続き時に「住宅用家屋証明書」が必要となりますので、法務局北出張所で登記申請を行う際に原本還付請求を行ってください。
郵送での申請
住宅用家屋証明書の郵送による申請を受け付けています。申請方法・注意事項をご確認のうえ、お送りください。通常の窓口での証明書交付よりもお時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。お急ぎの際や、詳細な書類審査が必要となる未入居での申請はできるだけ窓口までお越しください。
申請方法
お送りいただく書類
- 住宅用家屋証明の申請書類一式
- 定額小為替(1件につき1,300円の手数料が必要です。)
郵送での現金の授受及び釣銭の対応はできませんので、定額小為替1件あたり1,300円分を過不足なくお送りください。定額小為替が同封されていない場合は受付ができません。 - 返信用封筒
宛先を記入した、対面手渡しとなるレターパックプラス(赤)を同封してください。(追跡機能がない返信用封筒では返送の対応ができません。) - 担当者氏名と連絡先
書類の不備等があればご連絡させていただきます。日中にご連絡できる電話番号をお知らせください。
送付先
〒116-8502 東京都荒川区荒川2丁目11-1
荒川区役所 北庁舎3階 (防災都市づくり部建築指導課) あて
注意事項
- 郵便事情により、郵送にかかる日数が通常より遅れる場合があります。
- 郵便事故については、区は責任を負いません。
- 申請の際は、レターパック等追跡機能がある方法で書類を郵送してください。なお、返信用封筒もレターパックプラスをご使用ください。
- 当課に到着したものから順次審査を行いますので、証明書の発送日について個別の要望にはお答えできません。
- 書類の不備等により証明書を交付できない場合がございますので、不備がないか必ず封入前にご確認ください。
- 誤記載や記入もれ、不足書類がある場合は証明書を交付できません。特に原本を必要とする書類に不備があった場合は、ファックスやメールでの対応ができかねますので、窓口にご来庁いただき修正をしていただく必要があります。郵送でのやり取りは行いません。
電子での申請
住宅用家屋証明書の電子による申請を受け付けています。申請方法・注意事項をご確認のうえ、お送りください。通常の窓口での証明書交付よりもお時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。お急ぎの際や、詳細な書類審査が必要となる未入居での申請はできるだけ窓口までお越しください。
申請方法
申請URL及びQRコード
https://logoform.jp/form/bUir/1349663
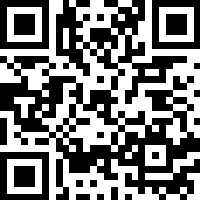
添付いただく書類
- 住宅用家屋証明の申請書類一式(証明書は区で作成し、郵送交付いたします。)
注意事項
- 領収書は発行できません。
- 決済は審査後です。クレジットカードまたはPayPayアカウントでのお支払いとなります。
- 一度お支払いされた手数料等は返金できません。
- 証明書の証明日については区が支払い手続きの完了を確認した日になります。当課に届いたものから順次審査を行いますので、証明書の発送日について個別の要望にはお答えできません。
- 郵便事情により、郵送にかかる日数が通常より遅れる場合があります。
- 郵便事故については、区は責任を負いません。
- 書類の不備等により証明書を交付できない場合がございますので、不備がないか必ずご確認ください。
- 誤記載や記入もれ、不足書類がある場合は証明書を交付できません。メールでのやり取りに時間を要する場合がございますので、ご了承ください。
- 1件につき1300円+郵送料金です。また、郵送については1件ずつの送付となります。まとめての発送は承っておりません。
事前相談
相談の内容によっては、事前にファックスまたは電子メールにてお問合せください。
- ファクス:03-3802-0046
- 電子メール:kenchiku@city.arakawa.tokyo.jp
受付時間
平日午前9時から午後4時30分(午後4時30分を過ぎてのご申請の場合、発行が翌日以降となる場合がございますので、ご注意ください。)
なお、正午から午後1時までの間に申請書類を受け付けたときは、証明書の交付は原則午後1時以降になりますので、ご留意ください。
申請書様式一覧
- 住宅用家屋証明申請書(ワード:25KB)両面印刷をしてご利用ください。
- 住宅用家屋証明証明書(ワード:29KB)
- ※注釈 ご利用の環境によっては、書式が正確に表示されない場合がございますので、下記PDFも併せてご参照ください。
- 住宅用家屋証明申請書(PDF:73KB)
- 住宅用家屋証明証明書(PDF:9KB)
- 家屋未使用証明書(ワード:31KB)
- 未入居の申立書(ワード:30KB)
- 親族等の証明書(ワード:31KB)
- 増改築等工事証明書(ワード:46KB)
- 入居見込み確認書(ワード:16KB)
お問い合わせ
防災都市づくり部建築指導課管理・監察係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線2841)
登記手続きについては、東京法務局北出張所にお問合せください。
所在地 北区王子6丁目2番66号 電話 03-3912-2608
登録免許税(租税特別措置法)については、荒川税務署にお問い合わせください。
所在地 荒川区西日暮里6丁目7番2号 電話 03-3893-0151