ページID:1390
更新日:2026年1月22日
ここから本文です。
復活!江戸東京伝統野菜
区内の伝統野菜に関連する情報をお伝えします。
あらかわの伝統野菜とは
その昔、江戸時代に荒川の地で生産されていた野菜があったことをご存知ですか?
江戸時代の荒川は、田畑が大部分を占める大都市江戸の近郊農村でした。江戸で消費する野菜は鮮度を保つため近郊で生産する必要があったため、江戸の市街地に隣接したあらかわの村々では、地の利を活かして、谷中(やなか)生姜(しょうが)、汐入(しおいり)大根(だいこん)、三河島(みかわしま)菜(な)など、荒川の地名を冠するブランド野菜を生産していました。
明治時代を迎え市街地の拡大や輸送方法の進歩などにより、農地は徐々に工場・宅地へ変貌し、これらのブランド野菜は、あるものは消滅し、またあるものは荒川の地名を冠したまま生産地を変えて全国に広まっていきました。
今、地域の資源として、改めてこうした伝統野菜に注目が集まっています。普及推進するための協議会や研究会が立ち上がり、さまざまに連携して活動しています。
荒川区においても、こうした伝統野菜に注目し、地域の歴史、文化や環境の変化を振り返るとともに、地域の貴重な資源の一つとして、現代の荒川の地に復活、普及させようという動きが始まっています。

当時の様子(道灌山下「東京真画名所図解」井上安治/画 荒川ふるさと文化館蔵)
あらかわの伝統野菜 いろいろ
「あらかわの伝統野菜」とひとくちにいっても、種類はさまざまあります。そのいくつかをご紹介します。
スジなし、香りよし「谷中生姜」
谷中生姜は、かつて荒川の地で栽培されていました。谷中本村(現西日暮里一丁目、二丁目付近)で栽培された葉生姜、それが本来の谷中生姜です。三河島や尾久でも栽培されていましたが、谷中本村で栽培されたものはスジがなく香りも良いとして、お盆の際には贈答品としても使われました。
栽培には、きれいな水と西日の当らない場所が必要とされ、谷中本村はその栽培に適した場所だったのです。関東大震災後、都心部の市街地からの人口流入等により、農地は格段に減り、戦前には、ついに谷中生姜は栽培されなくなりました。
現在、市場に出回っている葉生姜は千葉県などで栽培されたものですが、生姜の名前には「谷中」が冠され、葉生姜といえば「谷中生姜」となっています。

谷中しょうが(薑(きょう)「本草図譜」巻之四十四 菜部葷菜類 荒川ふるさと文化館蔵)
幻の漬菜「三河島菜」
江戸を代表する漬菜として、当時の書物にも描かれている三河島菜。味のよい漬菜として鷹狩りに訪れた将軍にも献上されたという記録も残っています。塩漬けにされ、冬場の貴重な葉物野菜として賞味されました。大きさは60センチほどにもなったとも言われていますが、茎が青いもの白いもの、葉が丸いものやイカリ型のもの、明治時代には、白菜のようにやや結球した姿も描かれ、本当の姿は定かではありません。その後、白菜が日本に伝わってきたことにより、栽培されなくなってしまいました。まさに「幻の野菜」になってしまったのです。
昨今、江戸東京・伝統野菜研究会の試みにより、この三河島菜の子孫種である「仙台芭蕉菜」の流れから、東京西部の農家で江戸東京・伝統野菜「青茎三河島菜」として栽培されるようになりました。復活を遂げたのです。

畑で育つ三河島菜
(平成24年4月小平市宮寺農園にて)
土地にあった野菜「汐入大根、荒木田(あらきだ)大根」
その昔、荒川の土地は大根の栽培に向いており、さまざまな大根が栽培されていました。その名が示すとおり、橋場村汐入(現南千住)で栽培された汐入大根、荒木田(現町屋)で作られた荒木田大根は、ともに、秋に種を蒔き年を越して春に収穫される二年子大根(「二年越しに作られる」という意味)です。汐入や荒木田の砂まじりの土地が大根の栽培に適し、特に良質のものが採れました。白首の細長い大根で、おろしや刺身のつま、煮物、漬物として幅広く食されました。

汐入大根

土から掘り出したばかりの汐入大根
(平成24年2月汐入東小にて)
ほかにもいろいろ
葉物野菜(小松菜、春菊、水菜など)
里芋や慈姑(くわい)、穂紫蘇(ほじそ)
枝豆(現在でも「三河島枝豆」という名前が残っています)
伝統野菜の復活に向けて
現在、荒川区内には、個人のお庭などでの栽培を除いて、農地はありません。
しかし、かつて荒川の地で栽培されていた野菜は、現在都内各地で復活に向けた取り組みが行われています。
こうした伝統野菜に目を向けることは、地域の歴史や文化に向き合うことにつながります。自分たちのまちが歩んできた道に思いを馳せながら、伝統野菜を味わうことができたら、地域への愛着も増し、食の楽しみも増えます。
荒川区でも、こうした伝統野菜を地域の大切な資源の一つとして、さまざまな視点からその復活と普及を目指していきます。
ここでは、そのような取り組みの一部をご紹介します。
荒川区外の主な取組
葛飾区にある東京都立農産高等学校(外部サイトへリンク)では、毎年授業の一環として三河島菜の栽培に取り組んでいます。葛飾区は荒川区と近隣で地質が似ており、あらかわの伝統野菜を栽培するのに適しているとのことから、平成24年に試験栽培が実現し、現在に至ります。(「復活!あらかわの伝統野菜」だより第1号より)(PDF:373KB)
栽培された三河島菜は、東京都立農産高等学校のご協力を得て、荒川区における各イベントでの販売、荒川区役所食堂でのアレンジメニューの提供など、幅広く活用されています。
東京都立農産高等学校の取組は、三河島菜を後世に伝えるための重要な取組であるとして、区長より感謝状を贈呈しています。
 |
 |
 |
| 三河島菜収穫(平成30年度) | 三河島菜販売(令和元年度) | 感謝状贈呈式(令和6年度) |
荒川区内の主な取組
区では、荒川区役所食堂「レストランさくら」にて、「三河島菜フェア」を期間限定で開催しています。
フェア期間中は、東京都立農産高等学校で育った三河島菜を使用した定食メニューを日替わりで提供しており、荒川区ゆかりの伝統野菜が食べられる貴重な機会として、好評をいただいています。
三河島菜は旬があり、生産量が限られていることから、フェア期間は短いですが、どなたでもご利用いただけますので、ぜひご賞味ください。
 |
 |
| 三河島菜ランチ(令和元年度) | 三河島菜の展示 |
あらかわの伝統野菜は、これまでもたくさんの方に支えられながら、復活に向けて様々な取組を行ってきました。詳しい活動内容は「復活!あらかわの伝統野菜」だよりをご覧ください。
その他
平成18年10月に、荒川区立荒川ふるさと文化館では、荒川のブランド野菜をテーマに「あらかわのお野菜 都市とお野菜」という企画展を開催しました。植物画や錦絵、古文書などから荒川を始めとする江戸の近郊農村で生産されていた野菜を紹介し、荒川の歴史的、地理的環境の変化などをさまざまな資料から紐解きました。
※詳しくは、企画展図録をご覧ください。同館で販売中(390円)。三河島菜などの絵が描かれたポチ袋も販売中(5枚組250円)です。図録は、同館学習室及び区立図書館にて閲覧もできます。)
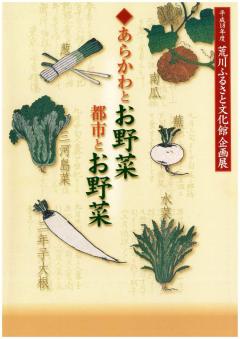
企画展図録(390円)

伝統野菜ポチ袋(5枚組250円)
荒川ふるさと文化館では、荒川区の歴史や文化財に関するさまざまな刊行物を発行・頒布しています。
また、文化館展示室入り口のミュージアムショップでは刊行物だけでなく、これまでに開催された企画展に関するグッズも取りそろえています。
引用・典拠ほか
- あらかわとお野菜 都市とお野菜(発行:荒川区立荒川ふるさと文化館)
- 江戸東京伝統野菜普及推進連絡協議会ホームページ
- 江戸伝統野菜通信(江戸東京・伝統野菜研究会 代表 大竹道茂氏 ブログ)
お問い合わせ
産業経済部観光振興課観光振興係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:461)